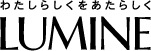アートブックは誰かに渡していくもの
もともと接客に興味を持ったのは、人の価値観に影響を与えられるクリエイティブな仕事だからです。店でお客さんが商品を買ってくれるのって、接客の会話のなかで価値観がちょっと変わった結果だと思うんですよね。
たとえば、お客さんのなかには「この作家の本ありますか?」とか、具体的に聞いてくださる人もいて。僕はそういうとき、その作家の本を勧めながらも、その周辺、たとえば「この作家が好きなら、この作家も気に入ってくれるかも」と、ほかの作家の本を紹介することがあります。そうやって、ご自身がもともと目的にしていたものじゃない本を買ってくれたときには、価値観に影響を与えられたのかもしれないと感じますね。
僕は、収集癖がまったくないんです。だから、自分のためにアートブックを所有することはほとんどありせん。やっぱり誰かに紹介して、その人が喜んでくれたりとか、新しいことを始めるきっかけになるようなことに興味があるんですよね。僕にとってアートブックは、自分の手元にとどめるものではなく、流れるように誰かに渡していくものです。

手触りや重さも表現の一部
2016年から「TOKYO ART BOOK FAIR」に携わるなかで、アートブックの表現がすごく豊かになっていると感じます。もともと本は“情報を伝える”という機能が一番重要視されていましたが、製本や印刷の風合いだったり、持ったときの重量感、そういうものを含めた総合的な表現に変わった。そのことにいろんな出版社や作家が気づいたことで、独自の表現を追求した本が増えているんだと思います。
来場者数も、2017年は約2万3千人だったのが、去年は3万5千人くらいになりました。アートブックっていつの間にこんなに人気になったんだろうって、びっくりしましたね。
僕自身がそうだったように、みなさんにアートブックをアートに触れる入り口にしてもらえたらいいなと思っていて。だから、TOKYO ART BOOK FAIRのディレクターをやらせてもらうことになったときに、会場のサイン計画など、視覚伝達の表現はすごく意識しました。「なんかちょっとかっこよくて、面白そうだから行ってみようかな」と、気軽に来てもらえるようなものを目指していて、それがたぶん、徐々に広がってきたのかもしれません。

持って、開く。その感覚を大切に
芸術とかアートって敷居が高いと感じてしまいがちなんですけど、僕は、食べ物を食べておいしいと思うのと同じだと考えているんです。最初は、1枚の写真を見てきれいだなと感じたらそれで十分。瞬間的に見て、自分の感想を持ってみるっていうところから始めるので全然いいと思います。
芸術に対する解釈の正解って、ないんですよね。かつて、現代美術家のマルセル・デュシャンは「芸術の解釈の50%は作家側にあるけれど、残りの50%は鑑賞者側にある」と言いました。アーティストの意図とはまったく違う解釈をしたとしても、50%は正解なんです。それくらい気楽にアートを見てもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。
アートブックを選ぶときには、手に取ってしっくりくるかということも重要です。本ってやっぱり3次元的なものなので、持ってページをめくるという体験自体もアートブックの一部なんですよ。そのときに自分がしっくりくる本っていうのは、おそらく、自分の感覚になにか訴えかけてくれる本。内容はわからなかったとしても、まずは1冊、その感覚を信じて買ってみるのがいいと思います。