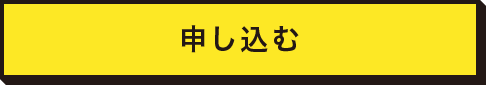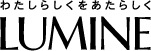500万人の「新しい走るひと」たち。
いわゆるランニングブームが始まったのが、東京マラソンがスタートした2007年頃。東京の街を3万人もの人が走るというイベントは、すごく大きなインパクトがありました。今、ランニング人口って1000万人いるらしいんですが、その内訳は、2007年以前から走っていた500万人と、東京マラソンあたりから新しく増えた500万人にざっくり分かれます。僕らは後者を「新しい走るひと」と呼んでいて、必ずしも競技を前提としていない、新しい価値観を持って走っているような「ひと」。距離も速度も頻度もさまざま、そして比較的年齢が若い。『走るひと』で紹介しているのは、その象徴となる人だったりします。
ブームといわれた当初は、そういう人たちをメディアが安易にカテゴライズしていました。「美ジョガー」なんて呼んだりして。でも、そうすると、どうしても一過性のブームになってしまいます。実際にブームが過ぎると離れた人も多くて。だから、カテゴライズするにしても、ちゃんと愛情を持ってやらないと、カルチャーとして育っていかないという想いが僕らにはすごくあるんです。
ようやくここ1、2年くらいで、ランニングのカルチャーと思えるようなものがいくつか出はじめている状況ですね。徐々に成熟してきて、ライフスタイルとして定着してきた段階。走るひとたちのファッションもこなれてきたなというのは、感覚としてあります。

リアリティのある、新しいファッションを。
ランナーのファッションも、細かいところでは変わっています。ちょっと前まではタイツの上にスカートを履いたりしていましたよね? 今はショートパンツだけだったりタイツ1枚だったり、どんどんシンプルになっていますね。『走るひと』でも、2号で初めてファッション企画をやって、CLASS ROOMの講座でゲストスピーカーに呼んだベイカー恵利沙と一緒に、リアリティのあるファッションを目指してつくりました。
というのも、今の段階では、モデルに着せてモードな世界観をつくっても、それがリアリティのない提示だったら意味がないと思っていて。だから、ランニングシーンの実際と誌面を、リアリティをもってつなぐために、全員、走っている人をモデルに。恵利沙とは、5キロ走れるかどうかがポイントだって話しました。極端な話、コンバースのオールスターとかで皇居を1周走るのって、けっこう辛いんです。だから、ウェアはスケートブランドでも古着でもいいけど、靴はランシューズにして、ちゃんと5キロを走るラインを保とうって。
恵利沙は、この企画をやった時点でフルマラソンを2回走った経験があって。走ることに巻き込んだのは僕なんですが(笑)、走っている人同士じゃないと共有できないリアリティみたいなものを生かしたスタイリングをしてくれました。家にある古着を着て走ってもいいよなっていう考えがあって。ヴィンテージのニルヴァーナのTシャツとか、そういう服とスポーツブランドの最新作の組み合わせもいいよねとか、そんな話をしていましたね。

新しいカルチャーを、ゆっくり育てていく。
今、僕らがやっていることって、ランニングへの入り口が競技だけだった以前の状況に対して、もっといろんな可能性を示そうということなんです。スニーカーを買ったらクッション性がめっちゃ良かったからちょっと小走りしてみたぐらいでいい。良くも悪くも、体育の授業なんかで、走るとはこういうことだという刷り込みがあって、辛いことだと思われている。そういう感覚を変えたくて。
『走るひと』に登場するのも、いわゆるランニングをする人だけではないんです。たとえばChim↑Pomのエリイさんは、SNSのプロフィールに「走るのが得意」と書いているのを見て取材したんですが、彼女にとってそれは、夜中に飲みに行くための終電に遅れるから駅まで走るということで(笑)。だから、「走るとランナーズハイになって気持ちいいよね」っていうテーマで、ドレスを着て繁華街や高級住宅街を走りまわるという表現にしました。
水曜日のカンパネラのコムアイさんもそう。日常的に走っているわけではないけど、新旧さまざまなランニングウェアをとにかくたくさん集めてきて、アーティストとしての感覚にヒントをもらいながら、一緒に議論しながら誌面をつくっていく。その結果、今までのランニングカルチャーにはなかった、新たなインスピレーションを与えてくれるような表現が生まれていったんです。
ランニングのカルチャーってまだまだこれから。僕らは今まで競技として認識されていたところに木を育てようとしていて、だからファッションやアート、音楽のカルチャーから学ぶところがすごくある。いろんなところから光を浴びたり、養分をもらったり……。リアリティを保ちながら、ゆっくりゆっくり、その木を育てていこうとしているんです。だからこそ『走るひと』をつくる意義があると思っています。そして、そこからスポーツや走ることとの新しい出会い方や関係性が生まれて、生活の一部として走るひとがもっと増えたらいいですね。